遺言書の有無を確認する方法
冒頭でもお伝えしたように、遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれの確認の仕方をみていきましょう。
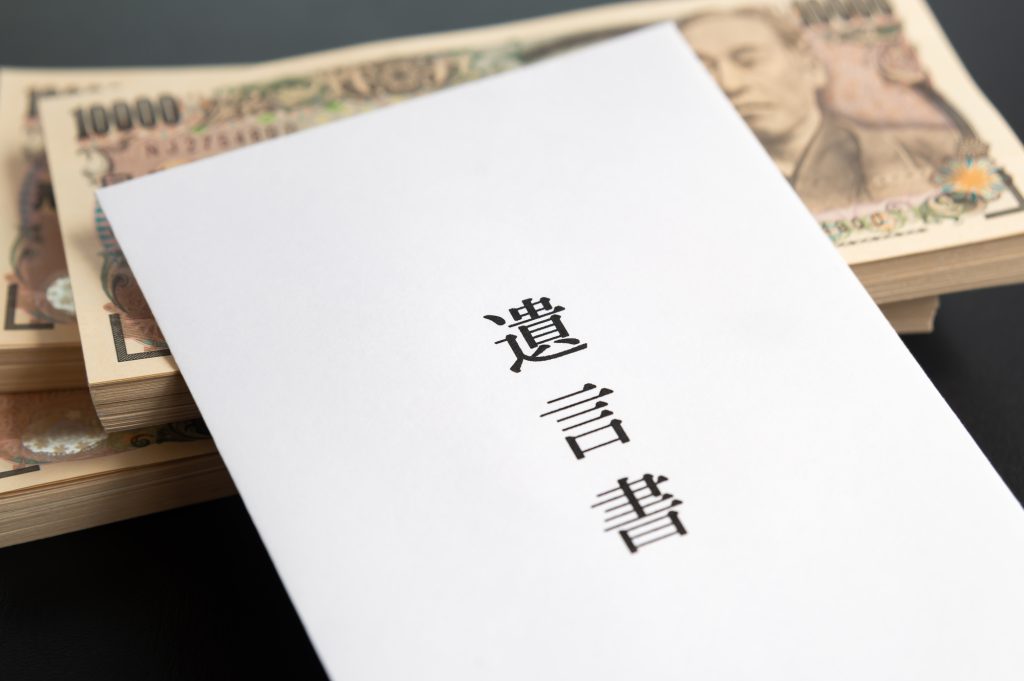
公証役場で公正証書遺言の有無を確認(検索)する方法
公正証書遺言は公証役場で保管されているため、相続人が照会の請求をすれば存在の有無を調べることができ、謄本を請求することができます。
1989年(昭和64年1月1日)以降に公証役場で作成された遺言書はすべて遺言検索システムによって確認することが可能であり、全国どこの公証役場でも検索することができます。
何らかの事情で謄本が滅失しても、復元ができるよう原本の二重保存システムも構築されています。
遺言書の有無を照会する場合に必要な書類
照会の請求をする人によって、必要書類が異なるため、下記でご案内いたします。なお、遺言者本人がお亡くなりになる前は遺言書の有無を確認することはできません。
- 相続人が照会する場合
- 被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍謄本)
- 相続人と被相続人の関係の戸籍(例:相続人が子である場合は、被相続人の除籍謄本と相続人の現在の戸籍)
- 検索を依頼する人の身分証明書と印鑑(認印で問題ありません)
- 代襲相続人が照会する場合(※代襲相続人とは、相続人になるはずであった子供や兄弟姉妹が被相続人よりも先にお亡くなりになった場合に、その子供が代わりに相続人になることです。)
- 被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍謄本)
- 代襲相続人ということがわかる戸籍謄本一式
- 検索を依頼する人の身分証明書と印鑑(認印で問題ありません)
- 相続人以外の受遺者が照会する場合
- 被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍謄本)
- 検索を依頼する人の身分証明書と印鑑(認印で問題ありません)
- 受遺者であることが想定できる書面(利害関係人でないかを確認するために必要となります)
- 受遺者が親族である場合には戸籍謄本等
- 委任を受けた司法書士などが照会する場合
- 被相続人の死亡戸籍
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人との関係の分かる戸籍
- 相続人の委任状
- 委任者の印鑑登録証明書(取得から3ヶ月以内のもの)
- 司法書士の身分証明書と印鑑(認印で問題ありません)
- 相続財産清算人が照会する場合
- 被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍謄本)
- 検索を依頼する人の身分証明書と印鑑(認印で問題ありません)
- 相続財産清算人であることが確認されたという家庭裁判所の決定
これらの必要書類を提出することで、遺言書の有無を確認することができます。
自筆証書遺言の確認方法
自筆証書遺言では、自己保管と法務局保管の二つの保管方法があります。

自筆証書遺言を自己保管してる場合
自己保管は、遺言者本人か管理しているため、遺言書の有無を確認するためには、実物を見つけ出す以外に方法がありません。
万一、遺言者自身が契約をしている金融機関等の貸金庫で保管をしている場合には、遺言者の死後にその貸金庫の開扉ができず、遺言書を取り出すことが不可能となり、実質的に遺言書を用いて相続手続きを行う事ができなくなるため、注意が必要です。
自筆証書遺言を法務局で保管してる場合
手数料がかかりますが法務局保管では、自筆証書遺言書保管制度というものがあります。
法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することができ、法務局で保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
生前に遺言者本人が遺言書を作成し、管轄の法務局の「遺言書保管所」に申請をする必要があります。この申請には予約が必要で、本人以外は申請することができません。
その遺言書の有無を確認したいときは、その保管してある法務局に対して遺言書情報証明書の交付請求をしなければなりません。
関連ページ
秘密証書遺言の確認方法
秘密証書遺言は公証役場で申述を行うと自己保管することになります。その為、秘密証書遺言の有無を確認する方法は遺言書を見つけるしかありません。ご本人が亡くなっている場合はご自宅や貸金庫などを探してみましょう。

まとめ
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
どの方式を選択するかによって必要書類や手続きの仕方、保管方法が異なるため、しっかりと確認してから作成することをおすすめいたします。
遺言書は遺言者本人の意思が形となって表れているものです。そのため、有無を確認する際には慎重に確認しましょう。
生前対策あんしん相談センターの遺言書に関する無料相談
当グループは、横浜、藤沢、渋谷に相談センターをおき、相続遺言生前対策において年間2,400件超の業務を担当しております。
相続手続きから、遺言書、成年後見、身元保証、生前の対策まで、幅広いご相談内容にご対応させて頂いております。豊富な実績を持つ専門家が担当いたしますので、まずはお気軽に生前対策あんしん相談センターまでお越し下さい。













